INTERVIEW 06
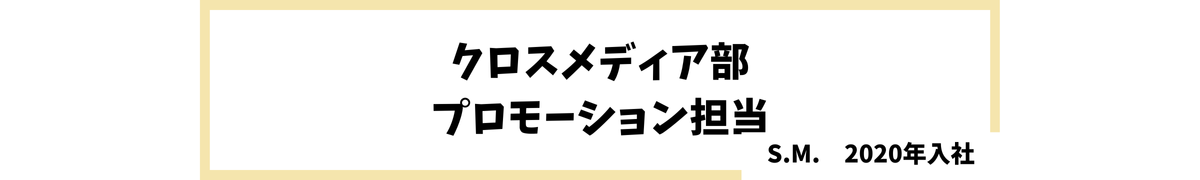
――入社の経緯について教えてください。
もともとは書店に勤務しており、日々本に囲まれて働けることに大きなやりがいを感じていました。一方で、発注や在庫管理などの業務では、使用していたシステムがやや使いづらく、改善の余地を感じることが多々ありました。そこから次第に、「書店で使うシステムを作る側に回ってみるのも面白いかもしれない」と思うようになったんです。好きな本や漫画に関わり続けながら、違った角度から支える働き方を模索し始めました。
そうした思いから、一念発起して、Webのプログラミング言語の学習をスタートしました。実際に取り組んでみると、ハードウェア系の開発にはかなりの専門性と難しさがあり、自分にとっては高いハードルであることを思い知りました。
一方で、Webサイトの制作進行など、コンテンツを“形にして届ける”行程には強い手応えを感じており、知識がある程度身についてきたタイミングで見つけたのが、ぶんか社の求人でした。出版とWebの両方に携わってきた自分のバックグラウンドを活かせる環境だと感じ、迷わず応募を決めました。
――入社当時のことを振り返っていかがですか?
入社したのは、クロスメディア部が発足して間もない時期でした。私が担当することになったスマートフォン向けのマンガサイトは、ちょうどサイトオープン直後の慌ただしさが一段落し、これから改善や課題解決に本格的に取り組んでいこうという段階でした。
漫画を配信するサイトの仕組みを理解するには新しい知識が必要で、改めて学び直すこともたくさんありましたが、運営方針をイチからメンバー全員で作り上げていく感じが、すごく面白かったです。
――現在のお仕事についても教えてください。
現在、クロスメディア部は2つのチームで構成されており、私はプロモーション課に所属しています。SNSやYouTubeチャンネルの運用をはじめ、デジタルメディアをフル活用したコンテンツの広報・宣伝が、主なミッションです。私自身は、前職のWebやITの知識を活かして、マンガサイトの運用やWeb広告のディレクションを主に担当しています。
特に力を入れているのが、WebサイトやSNSでよく見かける、「漫画が読める広告」の制作です。
作品のジャンルによって読者の興味を引くポイントは異なるため、まずは「このコマを見せたい!」という印象的なシーンを選び、そこからラフを起こして制作を進めていきます。
デザイナーや編集者と意見を交わしながら、一つの広告を作り上げていくプロセスはとても楽しく、興味を持ってもらえた時の手応えも、大きな励みになります。
――他にも幅広い業務を担当しているとか。
はい。最近では、実写ドラマ化に関する業務にも携わっています。制作会社、編集部、著者の方々の間に立ち、スケジュール管理や契約面での調整などを担っています。ドラマ化は関係者が多く関わるプロジェクトですので、著者の意向を尊重しつつ、テレビ局や制作会社と良好な関係を築きながら、すべての関係者が満足できるように調整していくことが大切だと思っています。さまざまな立場をつなぐのが、私たちの役割だと思っていますし、責任の大きな仕事ではありますが、完成した作品を目にした時は、「関わることができて良かった」と心から思える瞬間です。

――同部のクリエーション課はどのような部署ですか?
同じクロスメディア部の中に「クリエーション課」というチームがあり、そちらでは作品づくりを中心に行っています。電子書店でより多くの読者に届く作品を生み出すことを目指し、チーム間で知見を共有しながら協力体制を築いています。例えば、「この作品はSNSでバズりそう」「このターゲット層にはYouTube動画が響くかも」といった意見を出し合いながら、作品とプロモーションの方向性を一緒に考えています。
クリエーション課が生み出した作品を、私たちプロモーション課がしっかりと読者に届ける──。そうした流れを部署全体で意識しながら、得意分野を持ち寄り、新しいアイデアを形にしていく過程を、チームメンバー全員で楽しんでいます!
――YouTubeチャンネル「禁断書店」の登録者数が10万人を達成した時は、どんな気持ちでしたか?
「漫画をYouTubeで展開する」という発想は、当初は社内でもまだ浸透しておらず、手探りでのスタートとなりました。それでも、ボイスコミックを公開してみたところ、新旧問わず多くの方に視聴していただき、少しずつ手応えを感じるようになりました。
動画の本数を増やすことで業務量は増えましたが、そのぶん更新頻度が高まり、YouTube内での評価も次第に上がっていきました。
1本の動画で大きくバズることは少ないものの、地道に良質なコンテンツを発信し続けることが、結果として視聴者の信頼につながっていると実感しています。
また、コメント欄では「寝る前にちょうどいい」「家事をしながら楽しんでいます」といった声も多く寄せられています。
コロナ禍以降のライフスタイルの変化とも相性が良く、隙間時間に気軽に楽しめるコンテンツとして受け入れられているのではないかと感じています。
漫画作品を“読む”だけでなく、“視聴”という新しい接点を通して、作品の面白さがしっかり届いていると感じられることは、私たちにとって大きな喜びです!

社外のサイトにぶんか社作品を掲載してもらうことになり、ページのプレビュー画面をチェック。
マンガページ画像の並び順、テキストの誤字、紹介された単行本の購入先サイトURLなどが間違っていないかを確認します。
広告代理店から、前月Instagramで出したマンガ広告のレポートが届いたので確認。
内容、選んだコマ、タイムリーなストーリーだったかどうかなどで結果が変わるため、良かった点/改善が必要だと思われる点のヒントをレポートから読み取って翌月からの改善案を立てます。
誰かと一緒に行ける時はなるべく顔を出し、チームメンバーの趣味の話を聞いたりして、普段の会話のきっかけになる話題を得ています。
内容は主にぶんか社作品の売上ランキングや、各種SNSやプラットフォームで行っているマンガのプロモーションの結果報告、今後ピックアップしていくべき作品やジャンルの共有などで、メンバーそれぞれが情報を持ち帰り、担当業務に活かしていきます。業量調整の相談をすることもあります。
進行中の施策や実写ドラマ化にかかわる部内の制作物チェックや、サイトに新しく掲載する作品のデータ準備やサイトへの登録作業をおこないます。
サイト上に不具合などが見つかったら、発生条件や要望を整理した上で、制作を委託している制作会社へ改修を依頼します。
他編集部から作品のデジタルプロモーションの依頼を受け、打ち合わせ。企画の内容に応じて必要な人員やスケジュールを組みます。
サイトで実施中のキャンペーンへのアクセス数やSNS広告のクリック数の進捗を、各種分析ツールで確認。
わからないことはWebで調べたり、専門知識のあるメンバーや外部の広告代理店などにも聞きながら、実施中に軌道修正が可能な場合は対策を行います。
翌日の会議や打ち合わせに必要な資料や報告シートを作成します。